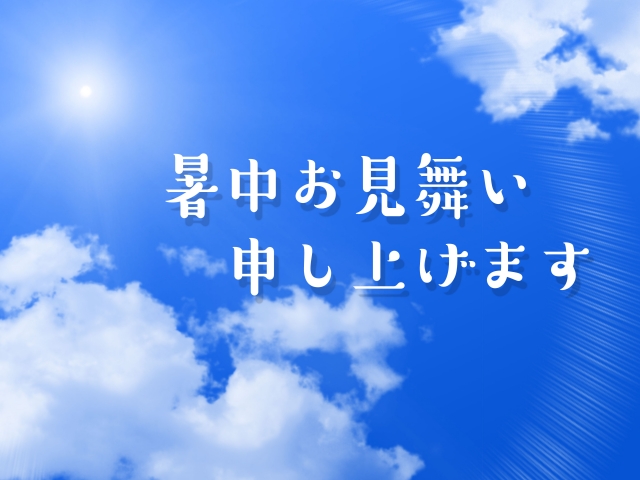私が子どもの頃は、当たり前のように書いていた「暑中見舞い」ですが、私の子どもたちときたら「暑中見舞い?なにそれ?おいしいの?」とか言う始末。
今は、スマホで簡単に繋がることができますし、時代の流れではありますが、少し寂しい気もしますよね。
しかし、そんな子どもたちも社会に出たら、上司やお世話になった人に暑中見舞いを出さなくてはいけなくなる日がくるかもしれないと思い、暑中見舞いの書き方をまとめてみました。
暑中見舞いの由来・起源
暑中見舞いは、お盆の贈答習慣に由来します。
昔、お盆に里帰りする際、ご先祖様への供養の品を持参する風習がありました。
それが、江戸時代になると、お世話になっている人への感謝の気持ちを表す贈り物へと変化していき(お中元の始まり)訪問して贈り物を渡せない場合には、飛脚便を使って書状を届けていました。
この書状が、明治時代、郵便制度の発達とともに挨拶状を送る習慣になり、大正時代に現在の「暑中見舞い」が定着しました。
暑中見舞い以外にも、「年賀状」や「寒中見舞い」「余寒見舞い」など相手の健康や繁栄を願って送る季節の挨拶状は、日本ならではのものです。

「暑中見舞い」の暑中っていつ?
暑中だから、暑い最中なのでしょうが、具体的にはいつをさすのでしょうか。
暑中は、二十四節気の「小暑」と「大暑」をさします。
- 小暑・・・7月7日頃~大暑(7月22日ごろ)までのおよそ15日間
- 大暑・・・7月23日頃~立秋(8月6日頃)までのおよそ15日間
小暑・大暑の日付けは、その年によって異なり、多少前後するものの、この小暑と大暑を合わせたおよそ30日間が「暑中」です。
「暑中見舞い」は、この「暑中」の期間に出すものですが、梅雨が明けてから8月はじめまでに届くように出すのが一般的です。
そして、立秋(8月7日ごろ)を過ぎたら、暑中見舞いではなく「残暑見舞い」にして、8月末までには届くようにします。

目上の方へ「暑中お見舞い申し上げます」は失礼って本当?!
「暑中お見舞い申し上げます」は、「あけましておめでとうございます」のようにもはや定型文となっていますが、マナー本などでは、目上の方に送る場合は不適切だと書かれています。
「見舞う」という言葉は、本来、目上の人から目下の人に使う言葉だからというのが理由のようです。
そのため、目上の方に暑中見舞いのハガキを出すときには「暑中お伺い申し上げます」「残暑お伺い申し上げます」とするのが正解なのだそう。
ただ、実際に販売している暑中見舞いのハガキで「暑中お伺い申し上げます」と書かれているものを見たことはないですし、そこまで気にする人は少ないのでは?と個人的には思います。
自分でパソコンで作成するときなどは、少し気を付けてみると、マナーに厳しい年配の方からは「おっ!」と思われるかもしれませんね。

暑中見舞いの書き方
暑中見舞いの書き方に特に決まりはありません。
ただ「見舞い」なので、相手の健康を気遣う言葉は忘れずに入れましょう。
- 挨拶
- 季節の挨拶+相手の健康を気遣う言葉
- 自分の近況報告・感謝の気持ち
- 相手の健康を祈る言葉
- 日付(省略してもよい)
【挨拶】
例:暑中お見舞い申し上げます/残暑お見舞い申し上げます。
【季節の挨拶+相手の健康を気遣う言葉】
例:連日、厳しい暑さが続いておりますが、ご健勝のことと存じております。
例:蝉の声が聞こえる季節となりましたが、お健やかにお過ごしのことと存じます。
【自分の近況報告・感謝の気持ち】
例:平素は何かとお世話になりありがとうございました。
例:私たち家族は、おかげさまで元気に過ごしております。
【相手の健康を祈る言葉】
例:暑さ厳しき折、お体にはくれぐれもお気をつけてくださいますようお願い申し上げます。
例:夏風邪などお召しになりませぬようご自愛くださいませ。
まとめ
今は、暑中見舞いどころか年賀状すら書かないという人が増えましたし、手書きのものなどほとんど見かけなくなりましたね。
ハガキを出しても、返事はメールやLINEだったりもします(^^;)
時代の流れを感じますよね~。
 RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>
RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>