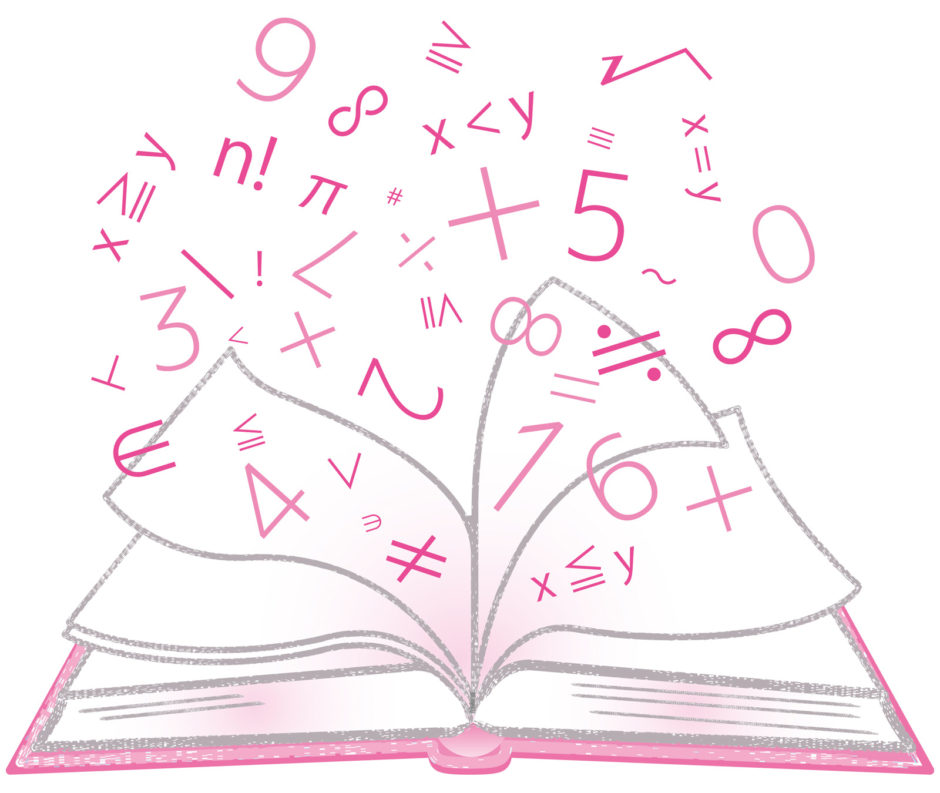学校でも職場でも必ずいる「頭のいい人」。
頭がいい=偏差値が高いと考える人が大半だと思いますが、偏差値の高さだけが頭の良さではありません。
確かに学生のうちは、テストの成績や偏差値が評価されますが、社会に出ればどうでしょうか。
偏差値が高くなくても、頭の回転が早かったり、発想力があったり、リーダーシップがあったりと、仕事で成功し、周囲から「頭がいい」と一目置かれる人はたくさんいますよね。
そんな「頭のいい人」には、特徴があります。
頭のいい人の考え方や行動、良い習慣を見習うことは、自分を変えるチャンス、頭がいい人に近づけるチャンスです。
そういうわけで、今回は、頭がいい人の特徴と、頭がいい人に近づくためにできることを紹介していきますね。
そもそも頭がいいってどういうこと?
そもそも「頭がいい」とはどういうことをいうのでしょうか。
一般的に「頭がいい」というと、偏差値やIQ(知能指数)が高い人のことをさす場合が多いと思います。
しかし最近では「IQ」とは違う視点の「EQ」という指数が注目されるようになってきています。
EQってなに?
EQとは、感情という視点から測定する指数で、いわば 心の知能指数(人間性)です。
成功者の多くが、情動を調整する能力に優れている傾向があるため、最近では企業の採用や人材育成などの判断材料にもなっています。
IQ(知能指数)だけが高ければいいというわけでなく、EQ(情緒指数)の高さも備わっている人こそ、本当に頭の良い人といえるでしょう。
EQを構成する要素
EQを構成する要素は大きく分けて「心内知性」「対人関係知性」「状況判断知性」の3つ。
心内知性(セルフコンセプト)
- 自分の価値観や長所・短所などを把握する自己認知力
- 自分の感情や考え、行動を調整する自己統制力など
対人関係知性(ソーシャルスキル)
- 主体的に物事に取り組もうとする自主独立性
- 柔軟性
- コミュニケーション力など
状況判断知性(モニタリング能力)
- 状況を客観的に観察し判断する能力
- 他人の気持ちを理解し汲み取っていこうとする能力など

頭の良さは遺伝する?
地頭の良さや才能は、両親からの遺伝によると聞いたことはありませんか?
いくら頑張っても結果が出ない人もいれば、授業中寝てばかりで勉強している姿を見たことないけど、テストでは好成績という人を目の当たりにすると、世の中には努力だけではどうにもならないこともあるのだと気づかされます。
実際は、生まれた時から地頭の良い人というのは ほんの一握りで、多くは教育や環境などの後天的な要素が大きいそうです。
確かに、子どもの頃に、様々な経験をさせ知的好奇心を伸ばしたり、読書や楽器演奏は脳の発達に良いなどといわれていますよね。
しかし、
「子どもの頃にやってこなかったし・・・」
「時すでに遅しだし・・・」
という人も多いでしょう。
諦めるのは早いですよ。
”なりたかった自分になるのに、遅すぎるということはない”
”なりたかった自分になるのに、遅すぎるということはない”
これは、夏目漱石も愛読していたといわれるイギリスの女性作家「ジョージ・エリオット」の言葉です。
頭の良い人の25の特徴をあげていきますので、真似できそうなことは実践してみるといいかもしれません。
自分を変えるチャンスだと思います。
また、自分の周囲の「頭のいい人」を思い浮かべつつ、当てはめてみても面白いと思いますよ♪

頭の良い人(頭のいい人)の25の特徴
頭のいい人には、特徴があります。
頭の良い人とじゃ、単に勉強ができる、偏差値が高い、知能指数が高いという人だけをさすのではなく、心の知能指数の高い人、仕事ができる人も含みます。
では、頭の良い人の25の特徴をみていきましょう♪
頭のいい人の特徴1:集中力がある
頭のいい人は、集中力があります。
余計な雑念にとらわれず、ひとつのことにじっくり取り組めるので、人よりも短時間で理解できたり、質の良い仕事をこなすことができます。
集中できる人が羨ましいとか、自分には集中力ないからな~と思っている人もいるかもしれませんが、実は「集中力」というのは誰でも身につけることができるんですよ。
集中力を身につけるコツは、後で紹介しますね。
世界的な指揮者である小澤征爾さんの名言にこのようなものがあります。
”集中力っていうのは、天才のものじゃないんだ。訓練だ。”
頭のいい人の特徴 2:適応能力が高い
頭の良い人は、適応能力が高いです。
周りがうるさいと集中できないという人が多いかもしれませんが、頭のいい人は、周囲の音シャットアウトし、集中して目の前の作業に取り組むことができます。
どんな環境下であっても、どんな制限があろうとも、工夫してやり遂げ、結果を残すことができます。
どうしても周囲の雑音が気になってしまうという人は、歌詞のない音楽を流したり(作業用BGMやクラシック)、耳栓をすると集中しやすいですよ。
頭のいい人の特徴 3:好奇心旺盛
頭の良い人は、好奇心旺盛です。
いつも多方面にアンテナを張っています。
探究心、行動力、チャレンジ精神があり、なんでも体験してみるので知識も経験も豊富です。
実際に体験することによって得た知識は、ただ頭で理解しただけの知識よりも、記憶としても定着しやすく、その結果、頭が良くなるというわけです。
現代物理学の父とも呼ばれるアインシュタイン博士の名言。
”私には特別な才能などありません。ただ、ものすごく好奇心が強いだけです”
頭のいい人の特徴 4:無駄な時間を過ごさない
頭の良い人は「時は金なり」を理解し実践しています。
「時は金なり」とは、時間はお金と同じくらい貴重なものだから、決して無駄にしてはいけないという意味のことわざですが、頭の良い人は、無駄な時間を過ごすことは無駄なお金を使うことだと考えています。
たとえば、2時間アルバイトをすれば1800円程度稼げますよね。
しかし、その2時間を何の目的もなくダラダラとスマホをいじって過ごした場合はどうでしょうか。
普通の人だったら、1800円稼げなかったと考えがちですが、1800円を払って、スマホをいじる時間を買ったと考えるのが、頭が良い人です。

頭のいい人の特徴 5:リフレッシュがうまい
頭の良い人は、リフレッシュが上手です。
頭の良い人は、ダラダラした無駄な時間を極力減らしたいと考えています。
勉強中や仕事中も、休憩を取らずに努力しているイメージがあるので、意外かもしれませんが、休憩を取ることの大切さを知っているのです。
集中力が途切れれば、効率が悪くなり、疲ればかりが溜まるので、自分の脳や体を適度に休ませることで、効率アップを図っています。
区切りが良いところまで進めてから休憩する人も多いと思いますが、集中力ということを考えると、〇分やったら休憩のように時間で区切るのがオススメです。
頭のいい人の特徴 6:オンオフの切り替えがうまい
頭が良い人は、働くときは働く、遊ぶときは遊ぶ、休むときは休むと、オンオフの切り替えが上手です。
頭が良い人=仕事人間というイメージもありますが、十分なプライベート時間を確保している人が多いのも特徴です。
仕事だけでも、プライベートだけでもだめということなんですね。
仕事を効率的かつ確実に終わらせ、遊ぶときも全力。
仕事中に遊ぶことを考えていたり、遊んでいるときに仕事のことばかり考えることはしません。
仕事も遊びも中途半端になってしまうからです。
頭のいい人の特徴 7:計画性がある
頭の良い人は、計画性があります。
細かい目標を設定し、計画的にスケジュールを組み、無駄がありません。
優先順位の高いものから効率的にことを終わらせることができます。
計画を立てることで、仕事の進行具合もわかりやすくなり、万が一の場合でも、引継ぎがスムーズにできるので、迷惑を最小限に抑えることができます。
行き当たりばったり、「なんとかなるだろう」と、とりあえず手あたり次第、目についたものから取りかかるのは非効率的。
余裕がないので予期せぬトラブルにうまく対処できなかったり、土壇場になって慌てたり、結局は時間内に作業が終わらないことになってしまうことも多いです。

頭のいい人の特徴 8:事前の準備に力を注ぐ
頭の良い人は、事前の準備に力を注ぎます。
仕事ができる頭の良い人ほど、自分で立てた計画にもとづき、時間を有効に使えるように、事前の準備はしっかり行うという特徴があります。
計画を立てるのも、準備をするのも時間がもったいない、そんな暇があったら、少しでも作業を進めたほうが良いのでは?と思うかもしれません。
しかし、事前に準備に力を注ぐことは、物事の成否を大きく左右します。
第16代アメリカ合衆国大統領のリンカーンはこのような名言を残しています。
”木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やす”
頭のいい人の特徴 9:冷静である
頭の良い人は、感情や勢いにまかせた行動はせず、冷静に対処することができます。
トラブルが起きた際、失敗した理由を精査せずに感情のままに怒ってしまう人も多いですが、決して動じず、落ち着いて対処できる人が本当に仕事ができる頭の良い人です。
感情や勢いにまかせて行動し、事を荒立て、言い争いをしたところで、なにも解決しないということをわかっているからです。
頼りがいがあって、カッコイイですよね。

頭のいい人の特徴 10:柔軟性がある
頭が良い人は、周りの意見や立場を尊重できる柔軟性を持ち合わせています。
例えば、周りと意見が対立することになっても、自分の意見に決して固執せず、周りの意見やアイデア、アドバイスにも耳を傾け、受け止めることができます。
問題を解決するべく、ものごとを様々な角度からみたり、考えを展開させたり、発想の転換をすることができるのが、頭の良い人の特徴です。
柔軟に対処できる臨機応変さは、企業で求められてる能力のひとつです。
頭のいい人の特徴 11:客観的に判断できる
頭が良い人は、客観的にものごとを判断することができます。
客観的とは、他の人の目線や立場など広い視野でものごとを見たり考えたりすることをいいます。
人の心や気持ちの変化を読み取ることに長けていたり、人の立場に立って発言や行動をすることができるので、人間関係がスムーズに運びます。
客観的の反対語は「主観的」ですよね。
自分の視点でしか物事を考えられず、視野が狭いため、他の人とトラブルになったり、失敗してしまいがち。
「客観的にみてみなさい」というアドバイスをよく耳にしますよね。
客観的に見ることで、今まで気づかなかった自分の長所や短所に気づくことができるため、人間としても成長することができるんですよ。
頭のいい人の特徴 12:説得力がある
頭が良い人は、言葉のボキャブラリーが多く、説得力があります。
例えば、ジャーナリストの池上彰さん。
政治や社会情勢など難しいテーマでも、子どもにもわかりやすいよう簡単な言葉に置き換えて説明してくれますよね。
難しい言葉や専門的な用語を多用し、知識をひけらかすのが頭の良い人ではありません。
また、長々と話したわりに「だから?」と言いたくなるような時ってありますよね。
結局何が言いたいのかわからない偉い人も多いですが、本当に頭の良い人は、相手にとって理解しやすい言葉を使い、伝える能力に優れています。
また、相手のレベルに合わせて、言葉を選び、話し方に配慮ができるほか、無駄を省き、要点を絞って人に伝えることができます。
アインシュタイン博士の名言。
”6歳の子供に説明できなければ、理解したとは言えない。”

頭のいい人の特徴 13:諦めない心を持っている
頭が良い人は、一定の成果が出るまで諦めずに作業することができます。
途中で投げ出したり、できない言い訳はしません。
諦めずに最後までやり遂げ、成果を上げた経験は、達成感とともに大きな自信へと繋がり、次に難しい事態に直面した時のエネルギーになります。
そのため、諦めない心を持つ忍耐力がある人は、成功を掴むことができるんですね。
すぐ諦めてしまう人は、逃げ癖や妥協癖がつき、信用も失ってしまいます。
言われたことをきちんとやるのは当たり前。それにプラスアルファのことができるのが頭の良い人の特徴です。
頭のいい人の特徴 14:失敗から学ぶことができる
失敗をしない人なんていません。
頭が良い人だって、もちろん失敗はします。
ただ、違うのは、失敗はしても同じ失敗は繰り返しません。
失敗すると、自分を必要以上に責めてしまう人、気持ちがくじけてしまい負のスパイラルに陥ってしまう人も多いですが、失敗もチャンスととらえることができるのが、頭の良い人です。
失敗して後悔するのではなく、失敗した原因や対策を考え、次の成功につなげることができます。
日本人は、失敗した人に厳しいなと感じることも多いですが「次の成功への足がかりができた」「失敗は挑戦の産物だ」「失敗により昨日の自分より成長できた」と、負のスパイラルに陥らないようあえて楽観的な思考を持つことも大切になります。
アインシュタイン博士の名言。
”失敗をしたことがない人間は、新しい挑戦をしたことがない人間である”
頭のいい人の特徴 15:ポジティブである
頭が良い人は、失敗したとき、何か困難にぶち当たったときも、ポジティブな発言や行動で前にすすむことができます。
ものごとに、困難や失敗はつきものです。
失敗のたびに、深く落ち込み、なかなか気持ちの切り替えができずに、周囲に気を遣わせるようではいけません。
一度、大きな失敗を経験すると、失敗自体が怖くなり、失敗を避けたいあまり、安全な道ばかり選択したり、逃げたいと思うこともあるかもしれません。
しかし、これでは確かに失敗する確率は減らせますが、そのかわり成長もしません。
頭の良い人は、「無理だ」とか「できない」などネガティブな言葉を滅多に口にしません。
自分の口から発したネガティブな発言は、モチベーションを下げ、気持ちまで負けてしまうことをわかっているからです。
そして、うじうじと長時間悩むのは時間の無駄、今やるべきことを考えて、その先を見据えた行動を起こすことができます。
電話機、蓄音機、白熱電球などを発明したアメリカの発明家、トーマス・エジソンの名言。
”私は失敗したことがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見つけただけだ。”
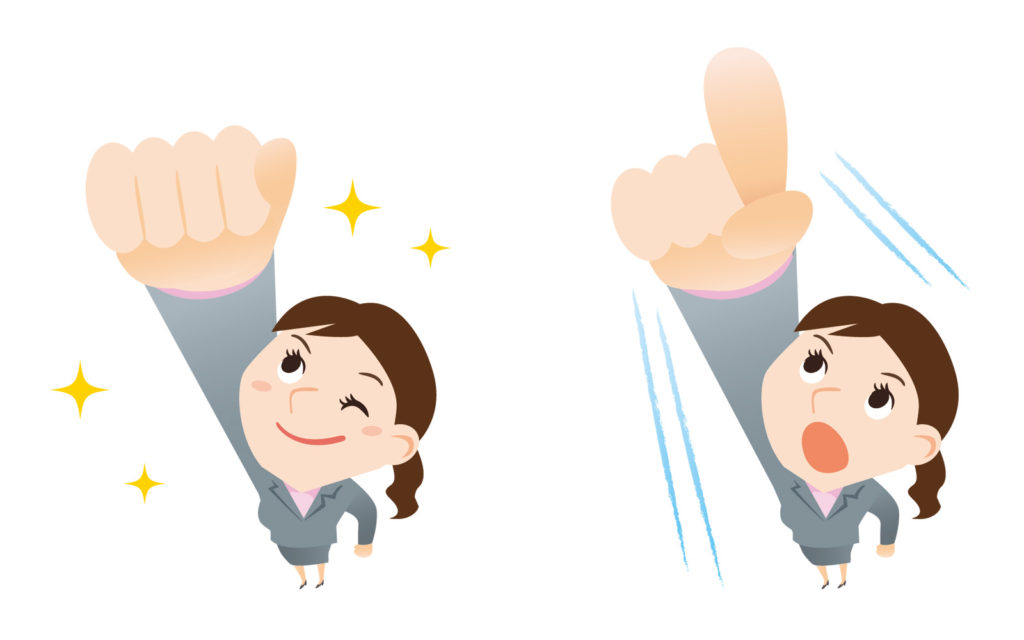
頭のいい人の特徴 16:逆境に強く努力を続けられる
頭が良い人は、逆境にぶつかっても、それをきっかけに学ぶことができ、克服するための努力をすることができます。
逆境を前にしても、今の苦労や、辛い気持ちも「後々役立つはずだ」「経験として活かせるはずだ」と、逆境を成長への糧と考えます。
負けずにコツコツと努力すればするほど、結果に繋がり、スキルアップしていくというわけです。
アインシュタイン博士の名言。
”困難の中に、機会がある”
頭のいい人の特徴 17:自分の意見を持っている
頭の良い人は、その場の雰囲気に影響されたり、流されることはありません。
自分の意見や意思を、しっかりと主張できますし、その場で最善だと思える方法を選ぶことができます。
現代では、ネットで誰でも手軽に知りたい情報を知りたいときに収集できますが、デマや根拠のない情報も溢れていますよね。
頭の良い人は、情報を鵜呑みにせず、情報の正誤をしっかり判断したうえで、インプットすることができます。
頭のいい人の特徴 18:先を見越して行動する
頭の良い人は、目先のことではなく、常に数歩先を見越して行動することができます。
あらかじめ起こりそうなトラブルなどを想定し、対策を取っているので、突然トラブルが起きても、慌てず対処することもできます。
わかりやすい例のひとつがショッピングです。
安さに釣られて衝動買いしたけど、まったく使わなかったとか、後悔した経験、誰もが一度はあると思います。
それが本当に今の自分に必要なものなのか冷静に考えることができ、長く使える良いものを選ぶのが、頭の良い人です。
「ハムレット」「ロミオとジュリエット」など多くの作品を生み出したイングランドの劇作家、シェイクスピアの名言。
”備えよ。たとえ今ではなくとも、チャンスはいつかやって来る”

頭のいい人の特徴 19:周囲をよくみている
頭の良い人は、周囲をよくみています。
周囲の人が何を考えているのか、何を必要としているのか、相手の意図や感情を察知して、思いやりや気遣いのある行動を取ることができます。
また、相手の気分を害さずに、自分の考えや気持ちも適切に伝えることができます。
人の気持ちに寄り添うことができる力「共感力」に優れ、自然な気配りができるので、周囲の人からも一目置かれた存在となれるのです。
頭のいい人の特徴 20:知識が豊富である
頭の良い人は、当然ですが知識が豊富です。
知識といっても、なにも学校で習った知識や、難しいこと、専門的な知識を指しているのではありません。
ニュースや今流行していること、ライフスタイルや趣味の知識、スポーツ、雑学など、広義的な意味での知識です。
幅広い知識は、円滑なコミュニケーションにも影響を与えます。
知識が多ければ多いほど、様々な人と話題を合わせることが可能だからです。
頭のいい人の特徴 21:コミュニケーション能力が高い
頭の良い人は、コミュニケーション能力が高いです。
相手のことを知り、理解しようという気持ちで接し、お互いの共通点を見つけることも上手です。
また、人の気持ちに寄り添うことができる力「共感力」にも優れているので、相手が話しやすいように心地良い雰囲気作りをすることもでき、初対面の人とでも、打ち解けるのが早いです。
そして、相手から学ぶことも忘れません。
コミュニケーションは、相手からの信頼を得て、ものごとを円滑に進めるには必要不可欠ですよね。
古代ギリシアの哲学者、アリストテレスの名言。
”垣根は相手が作っているのではなく、自分が作っている”

頭のいい人の特徴 22:素直である
頭の良い人は、素直です。
わからないことや疑問に直面したとき、知ったかぶりをして、わからないことをわからないままにはしません。
素直に「わからないから教えて欲しい」と伝えることができます。
こういう習慣がついているため、新しい知識が自然と増え、いざという時に、その豊富な知識を活かすことができるのです。
頭のいい人の特徴 23:他人と比較しない
頭の良い人は、容姿、性格、才能や実力、財力、評判など他人と比較しません。
この世の中に比べられるものは、数え切れないほどあります。
比べ始めたらきりがなく、他人と比較し、優越感に浸ったり、嫉妬しても、何も変わらないことを理解しているからです。
比べるなら「過去の自分」と、そして、最大のライバルも「過去の自分」です。
頭のいい人の特徴 24:頼るべきことは人に任せることができる
頭が良い人は、人を信じて頼ることができます。
自分だけの力では難しい場合は、周囲に相談したり、協力を求めることに抵抗はありません。
自分だけでやった方が早いとか、自分だけでやった方が納得のいく仕事ができるなどと、なんでもかんでも背負い込んで、いっぱいいっぱいになってしまっては本末転倒だからです。
まず自分が相手を信じて頼ることで、相手のやる気とモチベーションも高まり、そこに信頼関係が生まれます。
頭のいい人の特徴 25:自分を大切にしている
頭の良い人は、自分を大切にしています。
自分を大切にできる人は、気持ちに余裕が生まれ、自然と他人にも優しくなれるからです。
自分の時間(一人の時間)を確保して、趣味にじっくり打ち込んだり、体のケアをしたり、自分と向き合う時間も大切にしています。

頭がいい人になるための方法
頭がいい人になるには1:集中力を養う
頭がいい人は、集中力があります。
自分には集中力ないからな~と思っている人もいるかもしれませんが、集中力は、別に生まれつきの才能というわけではありません。
誰でも、なにも難しいことをしなくても養うことができます。
集中するコツは、簡単!
他のことは一切考えないこと!
これだけです。
ながら掃除、ながら運動など、~しながら〇〇する・・・といったような、ながら○○は一見、一石二鳥に思えますが、どちらにも集中できていない中途半端な状態であるといえます。
雑念が生じるもの(スマホ・テレビ・ゲーム機など)は遠ざけ、集中できる環境を作りましょう。
本を読むときは、本を読むことだけに集中するといった具合に、ひとつのことだけに集中する習慣をつけることが大切です。
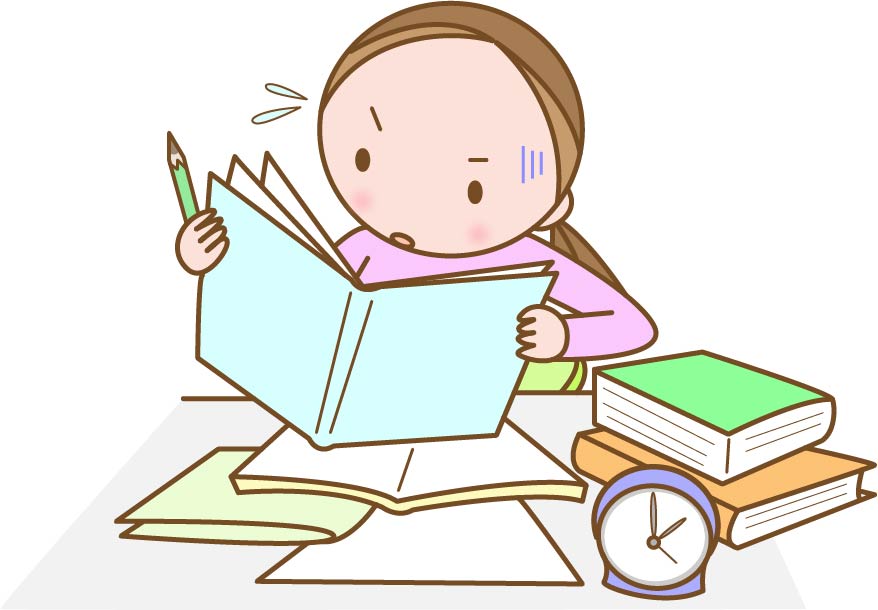
頭がいい人になるには2: 読書をする
頭が良い人は、読書を好んでしています。
マイクロソフトの創業者としてしられるビル・ゲイツさんも、「何時に帰宅しようが必ず寝る前に1時間の読書タイムを確保した」と言っていましたし、本を読む量と年収は比例しているというデータもあるんです。
近年、活字離れが進んでいるといわれていますから、普段から本をあまり読まないという人も多いのではないでしょうか。
しかし、頭の良い人になる一番手軽で、効果的な方法が「本を読むこと」です。
今は、インターネットでなんでも情報が手に入るから、読書の必要性を感じないという人も多いかもしれません。
しかし、インターネットの情報は、広く浅く、中には間違った情報もありますから、1冊の本の内容と同じだけの情報を得るのに時間がかかってしまいます。
また、広告やリンクをクリックしたり、関係の無い情報に目がいってしまったりと、誘惑が多く、じっくりと学ぶことができません。
特に、ビジネス本やノウハウ本は、著者が何年もかけて学んだことを、たった1冊読むだけで、たった数時間で、学ぶことができてしまうんです。
これってスゴイことですよね。
【本を読むことのメリット】
- 語彙力が増える
- 読解力を高めることができる
- 想像力が豊かになる
- 様々な知識が増える
- 疑似的体験が得られる
- 新しい価値観を知ることができる
- 違う立場からの考え方を知ることができる
- 過去の偉人を含め、成功者の考え方や生き方を参考にできる
どんな本を読めばいい?
頭が良い人になりたいからと、別に難しい本を読む必要はありません。
普段、読書の習慣がない人が、いきなり難しい本を読んでも挫折してしまうだけなので、まずは自分の興味があるジャンルで、自分のレベルにあった本から始めてみるのが良いと思います。
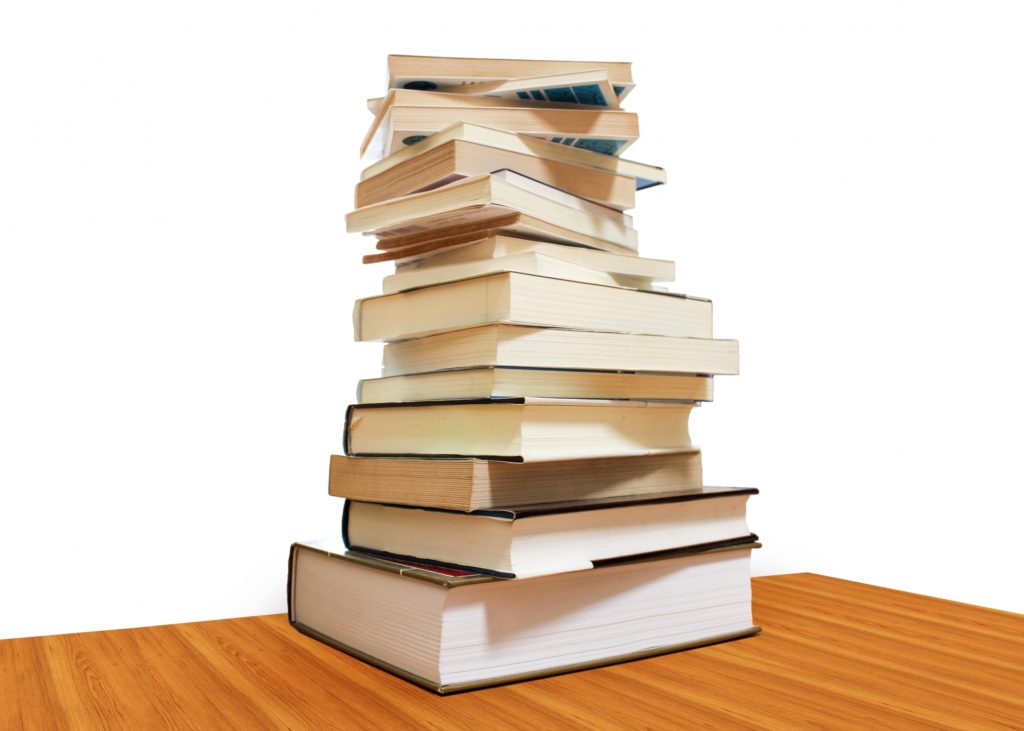
頭がいい人になるには3: 優先順位をつけ時間をコントロール
頭の良い人の25の特徴を紹介してきましたが、4「無駄な時間を過ごさない」6「オンオフの切り替えがうまい」7「計画性がある」などは、ひとことでいえば「時間の使い方がうまい」ということ。
時間をうまく使い、効率的に成果を出すために必要なのが、優先順位をつけ、優先度の高い順にものごとをこなすことです。
やるべきことの優先順位を見極め、効率的に作業をこなすためには、時にはやりかけのことをいったん保留するといった決断も必要になります。
大事な作業であればあるほど、なかなか実行にうつすのが難しいこともあるかもしれません。
- やるべきことをリストにする
- 自分の能力を考えて予定を立てる
- 計画通りに進むように時間をコントロールする
まずは普段の生活で、優先度を見極める力を養うのがオススメです。
誰しも、小中学校で「夏休みの計画」を立てた経験があると思いますが、これは時間の使い方を学ぶための勉強だったんですね・・・。

頭がいい人になるには4: 区切りをつけて作業する
頭が良い人って、仕事が早いですよね。
効率的に作業をこなすことができるからです。
毎日のルーチンワークは、集中することで短縮したり、いまやる必要ないことは、明日に回したり、集中が途切れているのに、だらだらと作業を続けることはしません。
時間がもったいないからと、休憩も入れず、ものごとを進めても、ミスが増えたり、イライラしたり、かえって時間がかかったりと、良い成果を得られません。
短時間で集中して作業をすることができるよう、休憩で上手にリフレッシュをしたり、時には15分程度の仮眠を取ることも必要です。
仮眠のスゴい効果!
仮眠というと「お昼寝」とか「怠けてる」といったマイナスのイメージが強いですが、厚生労働省が、午後の早い時刻に短い仮眠をすることが、作業能率の改善に効果的だと発表し、仮眠を推奨しています。
【仮眠のメリット】
- 脳が覚醒する・脳の疲れがとれる
- 作業効率がアップする・パフォーマンスが上がる
- 睡眠負債が返済できる
【仮眠のポイント】
- 午後1時~3時までの間にとる
- 仮眠の長さは、10~15分程度
- 横にはならないこと
なぜ10~15分なのかというと、20分以上になると体温が下がって深い睡眠に入ってしまうからです。
深い睡眠の時に無理に起きると、脳が眠っている状態になってしまい、脳や体が目覚めるのに時間がかかってしまうので、逆効果になるんですね。
外では眠れないという人は、目をつむってイヤホンで音楽を流し、外部からの情報をシャットアウトするだけでも効果が得られるということなので、試してみてはいかがでしょうか。

頭がいい人になるには5:流行に敏感になる
頭の良い人は、ニュースはもちろん、最近のトレンド、歴史、芸術、芸能・スポーツなど、本当に様々な知識を持っていますよね。
これらの知識は、自分自身のためになるのは当然ですが、特に他人との会話に活かされてきます。
知識が幅広いので、どんな相手とでも、会話を弾ませることができます。
何事からも学びを得られるよう、常に周囲に対し興味や関心を持っているからだと思います。
世代間の考え方や認識の違いも、なかなか面白く、その世代とコミュニケーションを取ろうとするときに役立ちます。
頭が良い人になるためには、周囲にアンテナを張り巡らせ、流行や他人が関心を持っているものに敏感になることも大切です。
頭がいい人にはるには6:全力で遊ぶ
頭がいい人は、仕事ができるので、仕事のことしか考えていない「仕事人間」なのかと思いきや、意外にしっかり自分の趣味の時間や、家族や恋人、友人たちと過ごす時間を大切にしている人が多いです。
私には、年が離れた子どもが3人います(長子は19歳、末っ子が6歳)が、長子が今年、就職しました。
カレンダー通りに休む業種で、ゴールデンウィークは10連休、お盆もしっかり9連休いただけましたが、社長は「遊ばない社員はいらない」上司には「仕事のことは考えず、しっかり遊ぶように」と言われたそうです。
子どもも「遊び」で成長するように、大人も「遊び」の中から学ぶことが多いのでしょう。
プライベートも充実させ、ストレス解消、しっかり気分転換することが、良い仕事に繋がるんですね。
趣味がない人はどうしたらいい?
いざ遊べ!と言われても、「趣味がない」「そもそも遊び方がわからない」という人も多いかもしれません。
遊べ!というと、アウトドアやスポーツ、旅行やレジャーを思い浮かべる人も多いと思いますが、仕事を離れて夢中になれるものならなんでも良いと思います。
例えば、散歩だって素敵な趣味だと思います。散歩中にいろいろな出会いや発見もあるかもしれません。
小中学生の頃、感想文を書くことや本を読むことが義務になっていたので本嫌いになってしまった友人は、カフェでコーヒーを飲みながら読書しているオシャレ女子に憧れて真似したら、ハマってしまい、今では本を片手にカフェ巡りが「趣味」になっています。
私はというと、手芸とガーデニングが大好きです。
子どもの頃は家庭科は苦手でしたが、自分の子どものために作り始めたらハマってしまいました。
ガーデニングだって、虫嫌いな私がハマるなんて・・・と、母親が驚いたほどです。
私や友人のような例もあるので、子どもの頃は好きではなかったものが、大人になって再びやってみたら楽しかったということもあります。
まずは様々なことにチャレンジする「趣味探し」にハマってみるのはいかがでしょうか?
【趣味の例】
- スポーツ・・・水泳・ゴルフ・筋トレ・ヨガ・マリン(ウィンター)スポーツ・マラソン・ダンス・ウォーキング
- パワースポット巡り・温泉巡り・遺産巡り・道の駅巡り
- ドライブ・ツーリング・サイクリング
- 散歩・食べ歩き
- 料理・・・パン作り・そば打ち・手打ちうどん作り・燻製作り・お菓子作り
- アウトドア・・・釣り・キャンプ・登山・バーベキュー
- 楽器演奏
- 映画・音楽鑑賞・ミュージカル鑑賞・スポーツ観戦
- ボーリング・ビリヤード
- 写真・カメラ
- 読書
- 書道・茶道・俳句
- DIY・手芸・陶芸
- 家庭菜園・ガーデニング・盆栽・苔玉作り
- プラモデル・鉄道模型・Nゲージ
- ジグソーパズル・クロスワードパズル
- 資格取得
- コレクション収集
- ネイル
- プログラミング
- ゲーム
- ボランティア活動

頭がいい人になるには7:人との出会いから学ぶ
頭の良い人は、人との出会いを大切にしています。
業種や年齢を問わず、自分とは違った価値観を持つ様々な人と会い、コミュニケーションをとることで、相手の気持ちを理解し、自分の感性を磨き、視野を広げる努力をしています。
イタリアの物理・天文学者であるガリレオ・ガリレイの残した名言。
”私は何も学びとることがないほど無知な人に出会ったことはない。”
コミュニケーション能力を磨くには?
コミュニケーションは、相手からの信頼を得て、ものごとを円滑に進めるためには必要不可欠なものです。
誰とでもコミュニケーションがうまく取れる人は、堂々としていて、自信に満ちあふれていて、本当に知的に見えますよね。
コミュニケーション能力を鍛えるためには、スポーツなどと同様、常日頃から練習も必要です。
損得や、好き嫌いで判断せず、まずは自分から警戒心を解いて話しかけることも大切です。
それが、コミュニケーション能力を磨く最初の一歩です。
【コミュニケーションにおいて重要なこと】
- 第一印象
- 伝える力
- 聞く力
- 相手の気持ちを汲む力
<第一印象>
よく面接を受ける際の注意事項などでも言われますが、第一印象で全てが決まってしまうといわれています。
その時間にして数秒のことです。
身だしなみはいうまでもありませんが、顔の表情にも注意しましょう。
挨拶は、挨拶と同時におじぎをするより、相手の目を見て挨拶の言葉を言い、言い終わってからおじぎをする方が好印象です。

<伝える力>
伝える力というのは、なにも難しい言葉を使用して、長々と話すということではありません。
相手の立場になって、手短に筋道を立ててわかりやすく伝えるということです。
これは一朝一夕で身につくものではなく、やはり日頃からの練習が必要になります。
文章を「5W1H」で要約する練習や、プレゼンテーションでよく使用される「PREP法」で文章を組み立てる練習がオススメです。
【5W1Hとは?】
- When・・・「いつ」
- Where・・・「どこで」
- Who・・・「 誰が」
- What・・・「何を」
- Why・・・「なぜ」
- How・・・「どのように」
【PREP法とは?】
- Point・・・「結論」
- Reason・・・「理由」
- Example・・・「事例・具体例」
- Point・・・「結論」を繰り返す
また、会話の中では、自分の体験談、失敗談などを入れて話すと、相手も理解しやすく、親近感を与えるので効果的です。
<聞く力>
話下手だからコミュニケーションが苦手だという人は、相手がどんどん話してくれるような雰囲気を作りましょう。
いわゆる「聞き上手」です。
【聞き上手になるには?】
- あいづちを打つ
- うなずきを入れる
- 話を要約して返す(オウム返し)
- 適度に質問する
<あいづち・うなずき>
あいづち・うなずきは聞き上手の基本です。
自分も話しているときに、あいづち・うなずきをしてもらうと、嬉しいしはなしやすいですよね。
「話をきちんと聞いていますよ」という姿勢や、共感を示すことができるとともに、相手は「自分の話が伝わっているんだ」と安心することができます。
<話を要約して返す>
相手の話のキーワードや、話の一部分を摘み取ってそのまま返すテクニックです。
オウム返しは、相手に共感を示し、安心感を与えるので、心理カウンセラーが使うコミュニケーションテクニックのひとつなのですが、使い方によっては「バカにしている」と感じる人もいるので、注意が必要です。
あまり繰り返して使うのは避けた方がいいと思います。
<質問をする>
聞き上手な人は質問上手です。
自分が話している時に質問されると「興味を持ってもらえた」と嬉しくなりますよね。
この時に使えるのが、さきほど「伝える力」でも紹介した「5W1H」です。
- When・・・「いつ」⇒「いつ?」
- Where・・・「どこで」⇒「どこで?」
- Who・・・「 誰が」⇒「誰が?」
- What・・・「何を」⇒「何を?」
- Why・・・「なぜ」⇒「どうして?」
- How・・・「どのように」⇒「どうやって?」
といった具合に、話の内容に応じて使うことができますよ。
ただ、あまりにも「5W1H」を頻繁に使うと、取り調べのようになってしまうので注意しましょう。
自分が聞かれたら困るなと思う質問はしないということを意識するとよいと思います。
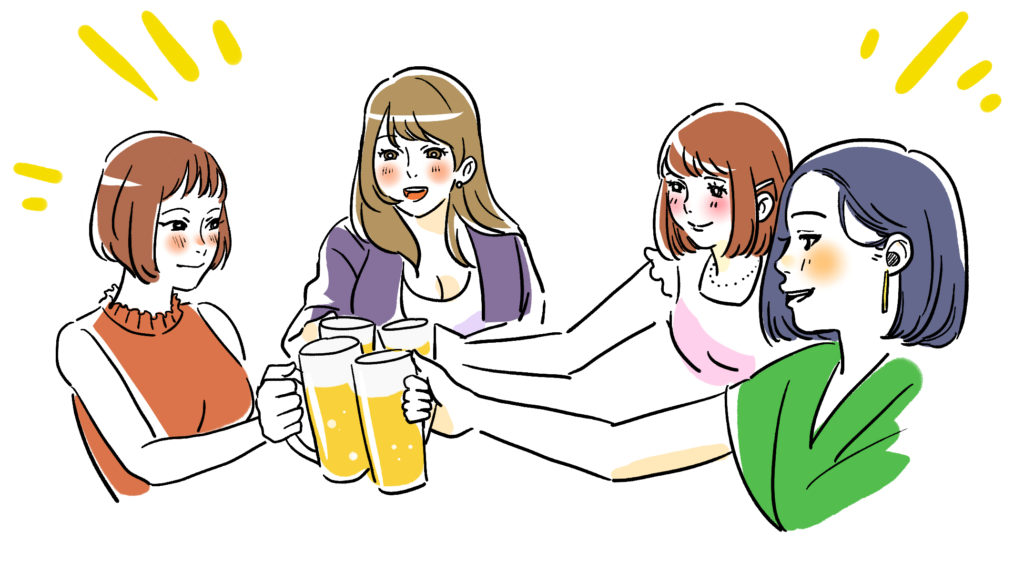
頭がいい人になるには8:他人と比較する癖を直す
人と自分を比較しては、うらやんだり、劣等感を覚えたり・・・ついついやってしまいますよね。
一見、容姿端麗で完璧そうに見えても、誰にでも悩みやコンプレックスはあります。
人と比較したところでなにもプラスにはなりません。
頭の良い人は「ポジティブ」です。
短所と長所は「表裏一体」短所は長所の裏返し、自分の欠点も「リフレーミング法」で長所に置き換えて、ポジティブに考えるようにしましょう。
(例)
- 飽きっぽい ⇒ 好奇心旺盛
- 優柔不断 ⇒ 慎重
- 自信がない ⇒ 謙虚
まとめ
頭がいい人の特徴と、頭がいい人に近づくためにできることを紹介しました。
学生時代の頭の良さと、社会に出てからの頭の良さ、IQとEQなど、頭の良さとひとことでいっても様々です。
頭の良い人の特徴、全てを実践することは難しいですが、ちょっと真似できそうなものもたくさんありましたよね。
今後、育児にも役立てたいなと思います。
 RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>
RELAX<ステキ大人女性のためのWEBマガジン>